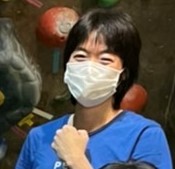アイスクライミングをやり始めて数年、冬の間は楽しいことがいっぱいあってアイスクライミングに集中してきませんでした。今シーズンはいつもより集中して取り組んだので忘れないように記録しておこうと思います。
アイスクライミングの動作について考えるべきこと、基本的なことなど、自分用に言語化しておこうと思います。
もし読む人が居たらあくまで参考までに。(私が色んな人から教わったり調べたり、考えたりしたことをまとめたものです)
ちなみに私が目指しているのは「力を使わず(苦しい思いをせずに)、安定して美しい氷を楽しむ」と言うことです。
来シーズンの自分に対する教訓(戒め)も込めて記録しておこうと思います。ちなみに私はビビりです。
アイスクライミングとはどういうクライミングか
アイスクライミングでトレーニング目標にするべきは「安定をつないで確実に登れる」ことだと思う(持論)。
「うわあ効いているかわからないアックスが抜けそう(腕でひきつけてプルプルしながら)」と怖い思いをしながら次のアックスを振るう。
「スクリュー決めたいけどパンプしそう!怖い!」
そんな登りは見ていてもヤバさが伝わってきます。。
氷は色々な条件があって、基本通りに動けないことも多いですが、基本的な動作は体に叩き込んでおきたいと思います。そのために今シーズンはかなり氷に通って練習しました。
ちなみにアイスクライミングを始めて「アイスは手も足もホールド自由」なんて教わったけど、最近は実際はそう単純ではないと感じます。
理由は氷は質も形状も色々あって、要はアックスを打てる場所が全然ないような氷の状態も良くあると言うこと。
特に長いルートでは色々な氷を突破する必要があって、アックスやスクリューが効きにくいセクションが出てきたりすることも良くあります。
氷をリードするなら落ちてはならない(当然だけど)
アイスクライミングは登る対象が氷であること、そして手や足に刃物を付けて登っていることから特にリードで登る場合は基本的には落ちてはいけないクライミングに当たります。
落ちてはいけないと言うのは「落ちればタダじゃすまない(怪我をする確率が高い)」クライミングと言うことです。
あまり限界ぎりぎりの難易度のクライミングを氷でやるのはあまり褒められたことではないと思います。
余談ですが最近はアックステンションを良く見ることがあります。もちろん技量が十分であっても氷の条件によって難易度が変わることはあるので落ちるくらいならテンションした方が良いですが、そういう条件の悪化を含めての難易度でもあります。またアックステンションするくらいならスクリューを決めてテンションしたほうが良いとも思います。アックステンションでもしアックスが外れた場合のリスクを考えると自分は怖くてできません。(リーシュを付けていたらアックスが顔面に向かってくるかもしれません。そんな事例を聞いたことがあります)
それと持論ですがテンションして登ったルートはフリーで抜けた(完登した)ことにはならないとは思います。もちろん何を目的にしているかと言うこともありますが。。
岩と違って落ちた時のリスクはもちろん、氷相手なので何が起こるかわからないし、氷のクライミングは基本「冬山」なので、様々な複合的なリスクがあります。自分でコントロールできる範囲で安定して登れる範疇の課題にトライするのが吉だと思います。
しっかりと技術を身に着けた上で憧れの課題にトライするほうが良いと思います。
基本はクライミング。ただしメンタルにも壁在り
アイスクライミングの基本の動きは岩や人口ホールドが対象の普通のクライミングと同じです。むしろ一般的なクライミングのムーブを氷に対してできるかどうかと言うところも大事な要素です。
アイスクライミングは打ち込んだアックスや氷を信用することができるかできないかでその次にどう動けるかが変わってきます。しっかり打ったアックスはまず外れないですが、外れないことと外れないと信じられることは別だからです。
過剰な心配は恐怖で動きを鈍らせますが、だからと言って楽観的になれるわけでもありません。
美しい氷を目の前にして、遠くから見ていた時はやる気満々でいざ取り付こうとすると恐怖心を感じることも多いです。そんな時は落ち着いて自分の実力で登れるかしっかり考えてからトライするか決めたいですが、怖気図いてしまうことも多いです。
そもそも単純にクライミングとして考えると、アイスクライミングのクライミング的強度はそれほど高くはありません。ですので夏の岩でのフリークライミングで大した成果を上げていなくても特に問題にならなかったりします。ただし一般的なクライミングの動作を氷の壁の中でできるか?と言うのはメンタルも重要になってきます。
気持ちで負けていつも通り動けなくなってしまうことも(自分にありがち)。
何とか打破したい!
クライミングと恐怖心はビビりには永遠のテーマですが特に氷を登る中で傾斜が変わったり、高度感や露出感が増したり、足元が切れてたりするとたまらなく恐怖を感じたりして、ストレスに耐えられなくなります。
アイスクライミング特有の動き
アイスクライミング特有の動きとしては、道具を使ってホールドを作るということです。既に存在するホールドを使うロッククライミングとの大きな違いです。アイスアックスとアイゼンを使って壁に対して手がかり足がかりを作りながら壁を登っていきます。
つまり、ホールドの場所や形状に限定されずに動けるというわけです。この部分がキモになってきます。
限定されたホールドではなく自分でクライミングを組み立てていくと言う要素がより顕著になります。
おすすめのアイスツールはこちら
一応今期使い始めていいなと思ったアイスツールをメモ。
アイスクライミングの登り方
アイスクライミングは氷にアックスを打ち込んで、アイゼンで足場を作って手と足を使って氷の壁を登っていく、と言うことになる。
これら一つ一つの動作は次の動きに全て繋がっている。一つ一つの動作と意識すべきことを中心にまとめておこうと思う。
基本的には先輩に教わったこととか、フォームを撮影して自分なりに考えたこと等が元になっている内容なので、正しいか正しくないかはわかりませんので、参考にする場合は自己責任でお願いします。
基本動作は同じことの繰り返し
基本的な動作は以下を繰り返しつつ登っていく。
②打ったアックスにぶら下がり足を上げて立ち上がる
①→②→①・・の繰り返し
②打ったアックスにぶら下がり足を上げて立ち上がる
①次のアックスを打つ
まずはアックスを氷に打ち込んで、手がかりを決める。アイスクライミングではアックスが抜けない限り足が崩れてもフォールすることはない。
また十分に信用できないアックスでは精神的にも次の動作に繋げられない。
アックスの打ち込みは確実に行い、抜けないようにアックスを決める。
①-1アックスの握り方・打ち方(振り方)
まずはアックスの持ち方に注意したい。アックスは握りこまず、親指と人差し指で挟み、この二点を支点にしてブラブラと振れるようにする。
握りこんでアックスを振ると腕がつかれるが、ゆるくアックスを持った部分を支点になるように持ち、氷に向けて放り投げる感じでアックスの重みを生かして、振り・打ち込む。
そのためにアックスは握りこまず、支点を中心にゆるく持つだけにする。
①-2アックスを打ち込む場所を決める
アックスは適当に打たずに氷をよく観察して、打ち込む場所を決める。氷には打ちやすい場所、打ちにくい場所、氷が壊れやすい場所がある。また、アックスを打った後は足を上げることになるので、足をどうあげるか、その後の動きを少し考えて打つ場所を決められると良い。
落ち着いて氷を観察しアックスをどこに打とうか、と決める。氷と対話するのだ(言いたいだけ)。
またその後のライン取りの考慮が必要な場合もある。氷の登攀ラインでは基本的に弱点を突いて登ることを考えたい。一手一手のアックスの打ち込み、打ったアックスを中心に次のムーブを起こすのでまずはアックスを決める位置は進行方向になる。
基本的にはアックスを遠くに打ち込みすぎないほうが良い。遠くに打ち込みすぎると身体が伸び切ってしまって次の動きにつなげにくくなる。これは普通のクライミングでも遠くのホールドをパツパツでつかんだときに懐に空間が作れなく足上げが苦しくなることを想像するとわかりやすいと思う。
(もちろん遠くに打つ場合もある)
①-3アックスを打ち込む
アックスを大きく振りかぶって氷に打ち込む。
アックスは背中後ろ(背中側)に振りかぶるが、強く握らず、ブラっと背中に当たる感じになる。
そこで頭の真上を通して壁の狙った場所に正面から打ち込む。
真上に打ち込めると良いのだが、氷の形状によっては打てる場所が限られたり、ピックの向きが内向き、外向きになる場合もある。
アックスを振る時は、手首を返したりしない。打ち込むときには曲げた腕を振りかぶった後にまっすぐに伸ばして、ピックが壁に垂直に当たるように意識する。
アックスを振る時に「手が先に氷に当たって邪魔」と感じる人は振り方が良く無い可能性が高い(自分もそうだった)。
角度を付けずに壁に向けて腕をまっすぐにする、後はアックスの重みでピックが壁に向かってスイングされ、壁に突き刺さる。
アックスがブレる場合は脇に緊張をもって、アックスがブレないようにする。
氷が固いほどまっすぐ芯の通った振りからくるスイングが重要になる。
①-4アックスの効きを確認する。
アックスを打ち込んだらアックスが効いているか確認する。上のアックスを支点に足上げをするため、上のアックスが外れたらフォールすることになる。
明らかに効いているときは良いが、不安があるときは必ずアックスが確かに効いていることを確認したい。下側に引いたり過重してテスティングする。
②打ったアックスにぶら下がり足を上げて立ち上がる
ここまででアックスを決め、決まったことが確認出来たら次の動作に移る。
決めたアックスを使って体を上げて、次のアックスを打つ準備に入る。
②-1アックスにぶら下がる
上にアックスを決めたとき、腕は伸びているはずなのでそのまま腕を伸ばしたままアックスにぶら下がる。重心を落とし、上のアックスに腕でぶら下がって全過重するイメージ。この際アックスのハンドルを握りこまず、小指をグリップエンドに引っかけているような感じ。
なんだか前腕がパンプしやすいな、と感じる人はここでアックスを握りこんでいる場合が多い。
握っているか確認するためには、アックスのグリップエンドから小指が離れていないか確認する。どうも小指が浮いている場合は、確実に握りこんでいる(自分もそうだった)。握りこむな!
イメージとしてはジムの長物でガバに手をかけている感覚。
上のアックスには必ずぶら下がること(可能であれば)。理由はアックスにぶら下がっていないと足上げを良い位置にできないから。次の項目を参照。
②-2足元をしっかり確認して、足を上げる(蹴りこむ)。良いポジションを作る(大事な行程)
上のアックスにぶら下がったときに、懐に空間を作って足元をよく見て、上のアックスを中心に一番力を使わない位置に足を上げる。
一般的には上のアックスを頂点に3角形を作るというのが良いとされる、氷の形状や足がおけそうなところに合わせて調整する。
ここで足を上げる場所が次の動作に繋がる一番重要な「ポジション」を作ることになる。
このポジションは非常に大事で、上のアックスを中心に「力を使わずに楽に壁の中に、安定して立っていられる体勢」を作る。
足を動かすとき、上のアックスを手で握って腕の力でひきつけないことが重要。
完全にアックスにぶら下がるイメージで足を良い位置にあげないと、一番力を使わない省エネなポジションに入るための、足を上げができない。
アックスにぶら下がって楽な姿勢で足をあげる。
あまり足を上げすぎると一気に立ち上がることになるので、腕の引き付けが必要になる。
また氷の形状を見て、足がおけそうなステップに一気に無理してハイステップにしてしまうとかすると、体勢がわるくなりがち(良くやってしまう)。
そうなると、体勢がつらくなる。
一度体勢(ポジション)がつらくなると、その体勢から脱出するためには次のアックスを決めて体勢を立て直す必要があるが、変な体勢からは次のアックスを振りにくい。
このように一度変な体勢になると、アックスが決まりにくくなったり、アックスを触れる範囲が狭くなる(体勢が悪くリーチが小さくなる)ため、アックスがうまく決まらず、しっかりぶら下がれなくて、いいポジションを作れないと悪循環に入ってしまう。
こういう時はメンタル的にも怖くなってくる。
無理な体勢で上のアックスを引き付けると腕のパンプにもつながる。
一つ一つの動作を丁寧にやる。安定したポジションに入れれば何の力も使わずにスクリューも決められるはず。
②-3氷へのアイゼンの蹴りこみ方
足を上げる際のアイゼンの蹴りこみについて述べる。
アイゼンは下からやや上、足の向きは外からやや内向き(やや内股)を意識して蹴りこむ。氷の形状によっては思った動きができない場合もあるが、基本はこの意識。
下から上に蹴りこむのは歯の形状からわかる通り、決めやすく効きやすい。
外から内にするのは、立ち上がる時やに腰に力が入り安定しやすく、立ち上がった後もアックスを振る時に体幹に力が加わりやすい。
モノポイントの先の爪と一つ外側の爪が壁に当たっている状態が一番望ましい。
②-4アックスにぶら下がり、動かした足に立ち上がりつつ、壁に腰を近づける。
アックスにぶら下がり足上げの位置を決定し、氷にアイゼンを蹴りこんだら、最後は足に立ち上がる。
足に立ち上がる時は上のアックスは基本的には腕で引かない。
下半身の力で壁に入り込みながら腰を氷に近付けて、立ち上がる。
この時、けりこんだ足のつま先に力が入りがちだが、そこには力は不要なはず。
足のつま先に力はいると、つま先立ちになってしまったり、足裏がつらくなってくる。つま先立ちになるとアイゼンが外れやすくなるので特に注意したい。
前爪は壁に向かって垂直か少し下げ気味に刺さっているときが一番良く聞く。
「足に力入っているな」と感じたら靴の中でつま先が丸まっていることが多い。一旦つま先を開いてリラックスするようにする。
また、足に立ち上がる時に、上のアックスを持った手でひきつけないと立ち上がれない場合は、②-2のポジションづくりに失敗している。
ポジション(体勢)が悪いので、もう一度アックスにぶら下がって足位置を決め治したり試行錯誤する(練習では)。
もちろん必ず一番いい場所に足が挙げられない場合があるが、それは本チャンの氷でやむを得ない場合で、練習の時はポジションづくりをうまくやるべき。
普通に優しいグレードのガバ課題・足自由でクライミングしているときに、腕で引いて立ち上がらないであろう。それは足の場所が何も考えなくても上手く置けているからだ。
腕で引かないと立ち上がれないときは、上のアックスと足との位置関係が良く無いためである。上のアックスにしっかりぶら下がれていないと、足の良い場所が体で見いだせず、こうなる。
②-5壁に腰を近づけて上半身は反らす
上げた足に立ち上がり壁に腰を近づけたら、上半身はしっかり反らす。そうすると安定して氷をよく観察できる体勢になる。
次にどこにアックスを打つか、氷を観察して決める。
ポジションさえ良ければここまでの過程でほぼ腕に力は使わない。変に立体的な氷でない限りシェイクしながら登るなんてことにはならないはず。
下半身は壁に入り込み、上のアックスで体を支えるだけで握りこんだり腕に力を入れて引き付けたりしない。足と腰の緊張感でしっかり氷に立つ。そうすると、上半身がしっかり壁から離せて、次のアックスをしっかり振りかぶれる体勢をとれる。
さらに良いフォームでアックスを触れるので無理のないスイングができ、良い場所へアックスが打てればアックスは決まりやすい。
→「①次のアックスを打つ」 に戻って繰り返し。
良いポジションが良いアックスの振りに繋がり、良いアックスの振りは確実な打ち込みに繋がり、確実に効いたアックスは次にいいポジション(足上げ・ムーブ)に繋がる。というわけだ。
ポジションのタイプ
ポジションにはいくつかのタイプがある。
正体かカウンターかそれが混ざった状態かなどがある。氷の形状に合わせて使い分けるとよいが、少しカウンター気味を意識すると次のアックスが降りやすかったりする。
具体的には、右手のアックスを上に打った場合は、次の足は左足を少し右手からまっすぐ下あたりの位置に上げる。もちろん一番力を使わないポジションになるようにするのが優先。
こうすると、右手と左足が軸になる。例えば右手と右足が軸になると体が開いてしまう(クライミングのオープンドア的な感じ)。
右手と左足で対角の軸になっていると、次の左手のアックスを振るときに体の軸が効いて、アックスを振るときに体幹を効果的に使える。
また極端なカウンターをする場合は、上の手と逆の腰を捻って壁に近づけるのもあり。これはダイアゴナルをイメージするとわかりやすいと思う。
クライミング・ボルダリングで最初に覚えることが多いムーブ「ダイアゴナル」。このムーブ実際にやってみると難しいと感じる方も…
余裕があるときは単純な正体だけでなくカウンターもしくは少しカウンター気味を意識してもよいかもしれない。
とはいえ両足を近くにそろえたほうが安定感はある。メンタル的にもそちらのほうが安心できることも多い。
氷の形状や自分の状況に合わせて使い合わせられるようにどちらも身につけておきたい。
まとめ
あくまで自分で意識すべきことを自分のためにまとめたものです。理論的に間違っていることや勘違いしていることもあるかもしれないので、あくまで参考までに!
力任せのアイスクライミングなんてくそくらえじゃい!無駄に力まず、安全に楽しんで、美しい氷を登れるようになりたいです。